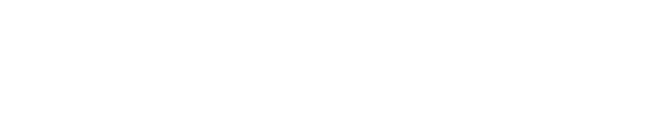- 家族葬ホール 空(Ku)
- > 豆知識

2025.01.21焼香の仕方|基本の手順と宗派別の作法
葬儀や法要に参列すると、必ず行う儀式のひとつが「焼香(しょうこう)」です。焼香とは、お香を焚いてその香りを仏前に供えることを意味し、故人やご先祖への供養、そして参列者自身の心を清める大切な行為とされています。
ただし、焼香の仕方や回数は宗派や地域によって異なるため、「正しい作法が分からない」「何回香をくべればいいのか迷う」と感じる方も少なくありません。本記事では、一般的な焼香の手順から宗派ごとの違い、マナーや注意点までを詳しく解説します。
焼香の一般的な手順
焼香には立礼焼香(立って行う)、座礼焼香(正座で行う)、回し焼香(席で順に回す)などいくつかの形式がありますが、流れはおおむね共通しています。
- 香炉へ進む
焼香の順番が来たら静かに立ち、祭壇に向かって一礼してから香炉の前へ進みます。 - お香を取る
香炉の前で合掌したのち、香箱から少量のお香を右手(または右手の親指・人差し指・中指)でつまみ取ります。 - お香を押しいただく(額に近づける)
宗派によっては、つまんだお香を額に押し付ける作法があります。これは仏様への敬意を表す意味を持ちます。 - 香炉にくべる
つまんだお香を香炉に静かに落とします。回数は宗派によって異なりますが、1回〜3回が一般的です。 - 合掌・一礼
焼香を終えたら合掌し、故人への感謝や祈りの言葉を心の中で捧げます。その後、祭壇に一礼して席に戻ります。
宗派ごとの焼香の回数と作法
焼香の回数や押す動作は宗派ごとに違いがあります。以下に代表的な宗派の特徴をまとめます。
・浄土真宗(本願寺派):1回のみ。お香は押しいただかず、そのまま香炉にくべます。
・浄土真宗(大谷派):2回。最初は押しいただき、2回目はそのままくべます。
・浄土宗:1〜3回。一般的には1回。お香を額に押しいただいてから香炉に入れます。
・天台宗:1〜3回。押しいただいてから香炉へ。
・真言宗:3回。いずれも額に押しいただいてから香炉へ。
・曹洞宗:1回。お香は押しいただかずに香炉へ。
・臨済宗:1回。曹洞宗と同じく押しいただかずに香炉へ。
このように、宗派によって回数や動作が違うため、事前に確認しておくと安心です。分からない場合は、
前の人の作法を参考にするとよいでしょう。
焼香のマナーと注意点
焼香は単なる形式ではなく、故人に祈りを捧げる大切な儀式です。次の点を意識しましょう。
・姿勢と所作を丁寧に
背筋を伸ばし、動作はゆっくり静かに行います。
・焼香の順番
一般的には、喪主やご遺族 → 親族 → 友人・知人 → 一般参列者の順番で行います。
・言葉を添える
焼香の際に声に出す必要はありませんが、心の中で「安らかにお眠りください」「ありがとうございました」
と感謝や祈りを捧げましょう。
・服装と安全に配慮
化学繊維やフリルなど燃えやすい衣服の場合は、火に近づく際に十分注意が必要です。
焼香の場面ごとの違い
- 通夜での焼香:参列者の人数が多いため、回数は省略して1回のみとする場合もあります。
- 葬儀・告別式での焼香:宗派に則った回数で丁寧に行います。
- 自宅でのお参り:線香を立てる代わりに焼香を行うこともあります。
焼香の際に気を付けたいこと
- 火傷に注意:お香や香炉は熱くなっていることがあるため、直接触らないようにしましょう。
- 静かに行う:会場全体が厳かな雰囲気に包まれているため、私語や大きな物音は控えましょう。
- 結果にこだわらない:回数や細かな作法よりも、心を込めて供養する気持ちが最も大切です。
まとめ:焼香は心を込めた供養の作法
焼香は、故人に祈りを捧げ、自分の心を清めるための大切な儀式です。宗派によって回数や作法は異なりますが、共通するのは「故人を偲び、真心を込めること」。
作法に自信がなくても、心からの祈りを込めて静かに焼香すれば、その思いはきっと故人に届くでしょう。
相談無料》家族葬ホール空 /葬儀/ 式場(大阪府藤井寺市/羽曳野市/柏原市/八尾市)
大阪府藤井寺市林6-6-35
家族葬ホール空
TEL: 072-936-0090 FAX :072-936-0080