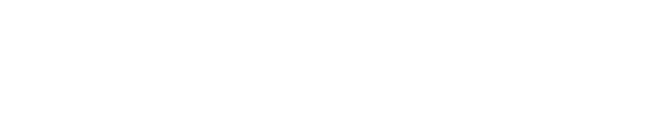- 家族葬ホール 空(Ku)
- > 豆知識

2025.09.10三途の川とは?
三途の川(さんずのかわ)とは、仏教の世界観において、現世(此岸)とあの世(彼岸)を分ける境界にあるとされる川のことです。
死者がこの川を渡ってあの世へ行くと信じられています。
三途の川の由来
・「三途」の意味: もともと「三途」は、仏教の教えにある「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」という3つの苦しみの世界(三悪道)を指す言葉です。
これらの世界に堕ちるか否かを分ける場所として、この川が考えられました。
・地獄道(じごくどう):絶え間ない苦痛を受ける世界。
・餓鬼道(がきどう):飢えと渇きに苦しむ世界。
・畜生道(ちくしょうどう):動物として生まれ変わり、本能のままに生きる世界。
この「三途」に落ちるか、それともより良い世界(人道、天道など)へ行けるか、
その分岐点にあるのが三途の川とされています。
つまり、三途の川は単なる境界ではなく、
死者の生前の業(ごう)が試される最初の関門としての意味合いが強いのです。
渡り方: 生前の行いによって、川の渡り方が3つに分かれることから「三途の川」と呼ばれるようになったとも言われています。
1.善人:穏やかな流れの浅瀬にある「橋」を渡る。
2.軽い罪を犯した人: 浅瀬を歩いて渡る。
3.重い罪を犯した人:流れの速い深みを泳いで渡る。
川の渡り方と「六道」の関係
三途の川を渡る方法は、生前の善行・悪行によって決まります。
この考え方は、仏教の「六道輪廻(ろくどうりんね)」の思想と密接に関わっています。
六道とは、人間が生まれ変わる6つの世界(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道)のことです。
・善人:仏や菩薩の教えに従い、善行を積んだ人々。
彼らは「橋」を渡ります。この橋は「金橋」や「銀橋」とも呼ばれ、何の苦労もなく対岸へたどり着きます。
彼らは六道のうち「人道」や「天道」へと進むとされます。
・一般的な人:善行と悪行が混在している普通の人々。
彼らは浅瀬の「山水瀬(さんずいぜ)」を歩いて渡ります。
水は膝下ほどで、流れも比較的穏やかですが、つまずくなどして苦労することもあります。
・重い罪を犯した人:殺人や嘘、盗みなど、悪行を重ねた人々。
彼らは流れが激しく、底なしの「江深淵(こうしんえん)」を渡らなければなりません。
そこには毒蛇や鬼がいて、死者を苦しめます。
彼らは六道のうち「三悪道」、特に「地獄道」へと引きずり込まれると信じられています。
三途の川の番人たち
三途の川のほとりには、死者の生前の罪を裁く、恐ろしい姿の番人たちがいるとされています。
・奪衣婆(だつえば):川のほとりにいる老婆で、死者の衣服を剥ぎ取ります。
・懸衣翁(けんえおう): 奪衣婆の隣にいる翁で、剥ぎ取られた衣服を「衣架の木」と
呼ばれる木の枝にかけます。木の枝のしなり具合で、死者の罪の重さを量るとされています。
衣服が重ければ重いほど枝が大きくしなり、罪が深いと判断されます。
この後、死者は閻魔大王をはじめとする「十王」の裁きを受けることになります。
三途の川の番人たちは、この最初の裁きに関わる存在です。
三途の川と関連する言い伝え
・初七日:仏教では、人は死後7日目に三途の川のほとりにたどり着き、最初の審判を受けるとされています。
・六文銭:死者が三途の川を渡るための渡し賃として、亡くなった人の死装束に六文銭を入れる風習があります。
・奪衣婆(だつえば)と懸衣翁(けんえおう):川のほとりには、奪衣婆が死者の衣服を剥ぎ取り、
懸衣翁がその衣服を生前の罪の重さを量る「衣架の木」に掛けるという言い伝えがあります。
・賽の河原:親より先に亡くなった子どもたちが、親への罪滅ぼしのために石を積む場所とされています。
しかし、積んでも鬼に崩されてしまい、永遠に積み続けるという悲しい話です。
三途の川の概念は、仏教の教えと日本の民間信仰が混ざり合って形成されたものと考えられています。
日本各地には、恐山の正津川のように「三途の川」と呼ばれる実在する川もいくつか存在します。
《相談無料》家族葬ホール空 /葬儀/ 式場(大阪府藤井寺市/羽曳野市/柏原市/八尾市)
大阪府藤井寺市林6-6-35
家族葬ホール空
TEL: 072-936-0090 FAX :072-936-0080