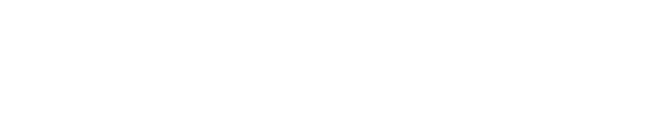- 家族葬ホール 空(Ku)
- > 豆知識

2025.03.27【完全ガイド】忌中と喪中の違いとは?期間・意味・過ごし方を徹底解説
身内に不幸があった際、よく耳にする「忌中(きちゅう)」と「喪中(もちゅう)」。
どちらも故人を偲ぶ大切な期間でありながら、その意味合いや過ごし方には明確な違いがあります。
「忌中と喪中はどう違うの?」「結婚式や初詣は行ってもいい?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、本記事では忌中と喪中の違い・期間・マナー・過ごし方のポイントをわかりやすく解説します。
忌中とは?
忌中(きちゅう)とは、故人が亡くなってから四十九日(仏式)または五十日(神式)までの期間を指し、
故人の魂がまだこの世にとどまっていると考えられる「特に慎ましく過ごすべき期間」です。
◆ 忌中の意味と由来
- 仏教では、死後49日間は魂がこの世をさまよい、極楽浄土へ向かうまでの期間とされています。
- この間、遺族は故人の冥福を祈り、日常生活を控えめに送る風習があります。
◆ 忌中の期間
- 仏教:故人の命日から四十九日まで
- 神道:故人の命日から五十日まで
※この期間が明けると「忌明け」となり、徐々に日常に戻っていきます。
忌中の過ごし方|避けるべき行動は?
忌中は、故人の冥福を静かに祈る時期として、以下の行動を避けるのが一般的です。
◆ 忌中に控えるべきこと
| 行動 | 理由 |
| 結婚式・お祭りなどのお祝い事への参加 | 慶事は故人を偲ぶ期間にふさわしくないとされる |
| 神社への参拝 | 神道では死を「穢れ」と捉えるため、参拝を控えるのが通例 |
| 旅行・宴会・パーティーなどの派手な行動 | 派手な行動を避け、静かに過ごすことが故人への礼儀 |
| 忌中札の掲示 | 自宅の玄関などに「忌中」の札を掲げることもある(地域差あり) |
喪中とは?
喪中(もちゅう)は、忌明け後から1年間を目安とした期間で、
故人を偲び、心の整理をつけながら慎ましく日常を送ることを意味します。
◆ 喪中の意味と背景
- 喪中は、心の喪失(=喪)に向き合う時間。
- 社会的には、慶事を控えるべき期間として認識されています。
◆ 喪中の期間
- 一般的には、故人が亡くなった日から一周忌(1年後)まで
- 故人との関係性によって喪中期間が異なることもあります
(例:両親や配偶者は長く、祖父母や兄弟姉妹はやや短い傾向)
喪中の過ごし方とマナー
喪中は、日常生活を送りながらも慶事を避けるのがマナーです。
◆ 喪中に避けること
| 行動 | 注意点 |
| 結婚式・賀寿祝いへの参加 | 招待された場合は事情を説明して欠席するのが丁寧 |
| 年賀状の送付 | 喪中はがき(喪中欠礼状)で年始の挨拶を控える旨を伝える |
| 派手な贈り物やお中元・お歳暮 | 時期をずらして送るか、控えめな品にする |
| 神社参拝 | 喪中中でも参拝は可能(忌中とは異なる点) |
◆ 喪中でも可能なこと
- 日常の仕事・学校生活:通常通り行う
- 仏事:法要やお墓参りなどは積極的に行ってよい
- 初詣:神社は忌中が明けていれば問題なし、気になる方は寺院へ
忌中と喪中の違いを一覧で比較
| 比較項目 | 忌中 | 喪中 |
| 期間 | 故人の命日から四十九日(仏式)または五十日(神式)まで | 忌明け後から1年間が目安 |
| 主な意味 | 故人の魂が旅立つ前の静かな供養期間 | 故人を偲び、日常に戻るまでの心の整理期間 |
| 結婚式・慶事 | 基本的にNG | 忌明けであれば、内容により可だが控えるのが望ましい |
| 神社参拝 | 控える(穢れの考えから) | 可(忌明け後であれば問題なし) |
| 年賀状 | 送らない | 喪中はがきを送って年賀状を控える |
| 表札・札の掲示 | 忌中札を掲げる場合あり | 掲示しないのが一般的 |
忌中・喪中のマナーは時代とともに変化している
近年では、家族構成や価値観の変化により、忌中・喪中の過ごし方も多様化しています。
- 「職場の忘年会に参加してもいいですか?」
→ 忌中中は控えた方が良いですが、喪中中であれば配慮の上、参加するケースもあります。 - 「神社で結婚式を予定していたらどうする?」
→ 忌中の場合は延期が望ましいですが、喪中であれば、親族間で相談の上決めることも可能です。
形式よりも**「故人を偲ぶ心」「まわりへの配慮」**を大切にする姿勢が重視されるようになってきました。
まとめ|忌中と喪中の違いを正しく理解して、心を込めた弔意を
忌中と喪中は、いずれも故人を偲び、心を整えるための大切な期間ですが、
意味や期間、マナーに明確な違いがあります。
◆この記事のまとめ:
- 忌中:亡くなってから四十九日(または五十日)までの特に慎むべき期間
- 喪中:忌明けから一周忌までを目安とした慎ましい生活期間
- 忌中中は神社参拝やお祝い事を控える必要あり
- 喪中は年賀状や慶事を控えつつも、日常生活は通常通り送ることができる
- 時代に合わせた柔軟な対応も大切だが、「心を込めた供養」が最も大事
大切な人を亡くしたとき、形式にとらわれすぎず、自分らしく故人を偲ぶ時間を持つことが、何よりの供養となるでしょう。
《相談無料》家族葬ホール空 /葬儀/ 式場(大阪府藤井寺市/羽曳野市/柏原市/八尾市)
大阪府藤井寺市林6-6-35
家族葬ホール空
TEL: 072-936-0090 FAX :072-936-0080